
親が負った多額の借金を子供が肩代わりして返済する話はよく聞きます。
亡くなったり、失踪してしまった親に借金があったら、残された家族の元へ督促の電話が掛かってくるでしょう。
しかし、いくら家族とはいえ、親が勝手に作った借金の返済義務なんてあるのでしょうか?
子供には親の借金を肩代わりする義務はない
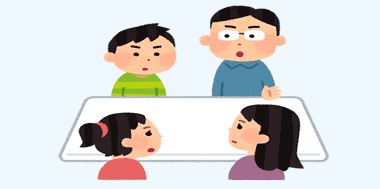
親に借金がある場合、贅沢をする為に借金癖があったり、ギャンブル癖で借金まみれといったケースは、そう多くはないです。
親が借金を負っている場合には「事業経営に失敗した」、「他人の保証人になった」、「祖父から事業と共に借金も相続した」といった、止む負えない事情の場合が多いです。
親に多額の借金があると、「子供である自分にも返済義務が発生してしまうのでは?」と心配する方もいると思います。
ですが、親の借金は親本人のものであって、原則として子供には一切、返済義務はありません。
借金の契約は、債権者と債務者、そして保証人だけが絡んでくるものです。
保証人にさえなっていなければ、同居している家族でも一切支払う必要はありません。
親を扶養する義務
民法第877条は扶養義務者の規定で、1項には次のことが書かれています。
「子供は親を扶養する義務がある」とよく言われますが、その根拠条文は民法第877条1項です。
法律で規定をされているので、実際に子供には親を扶養する義務があります。
ですが、扶養義務とは「扶養義務者の余力の範囲内」で行うものです。
子供に財力があり、資金的に十分援助可能なら、親の借金を肩代わりしても良いでしょう。
ですが、そうではなく子供は自身の生活で手が一杯で経済的な余力がない場合には、親の扶養義務があるからと言って、親の借金の面倒までみる義務はありません。
債権者の中には、親が借金返済できないとその子供に「親が困っているのなら、子供なら助けてあげて当然だろう!」と、さも正論の様に言ってくる方もいます。
ですが、親の借金の面倒までみる義務は子供にはないので、債権者には「子供には親の借金を返済する義務はない」と言って、突っぱねて返済を拒むべきです。
貸金業者の第三者への取り立て禁止
貸金業法21条は、貸金業者の取立て行為の規制について規定されています。
貸金業法21条1項第7号には、貸金業者の取り立て禁止事項として次の事柄が書かれています。
貸金業法21条1項第7号によって、貸金業者が債務者以外の人に債務者の代わりに借金の返済を要求することを禁止をしています。
債権者が貸金業者の場合に、「親の借金を代わりに払え」と言われたのなら、貸金業法21条1項第7号に該当することを告げて、法律違反行為であることを伝えましょう。
それでも止めずに、しつこいなら強要罪や脅迫罪が成立する可能性があります。
また、行政に未登録の違法貸金業者である闇金から親が借り入れをしていた場合は、貸金業法の取り立て禁止事項を無視した強引な取り立てをしてくる場合もあります。
何度も繰り返し、親の借金返済を子供であるあなたに要求するようなら、債権者とのやり取りを録音して証拠を確保した上で、警察に相談をすると良いです。
子供が親の借金の保証人となっていた場合

原則として、親の借金は子供には返済義務はありません。
ただし、親が借金をした時の借入契約の際に、子供が親の保証人になっていた場合は、子供にも返済義務が発生します。
なお、子供が親の保証人になっている場合でも、連帯保証人でなければ債権者に対して次の2つの主張ができます。
保証人の抗弁権
- 催告の抗弁権(民法第452条)
- 検索の抗弁権(民法第453条)
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、保証人に対して債権者が借金返済を要求した時に、保証人は、まず先に主たる債務者に催告をする様に請求できる権利の事です。
つまり、子供であるあなたは「先に親に請求をしてください!」と債権者に主張することができます。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、主たる債務者に弁済の資産があることを証明することで、先に主債務者に請求するようにと要求できる権利の事です。
つまり、子供であるあなたは「先に親の財産を差押えしてください!」と債権者に主張することができます。
なお、子供が親の借金の連帯保証人となっていた場合は、上記2つの抗弁を債権者に対して主張することはできません。
連帯保証人となっていた場合には、債権者は親と子供のどちらか回収しやすい方に借金の返済を要求することができます。
また、親が亡くなって、子供が相続手続きの際に親の財産の相続放棄をしたとします。
この場合、相続放棄をしたので、親の借金を受け継がずに済むのではと考えるかもしれません。
ですが、相続と借金の保証人は全く別な法律行為なので、たとえ子供が相続放棄をしたとしても、親の借金の保証人となっていた場合は子供には親の借金の返済義務があります。
親が勝手に子供を借金の保証人にしていた場合
身に覚えのない借金を債権者から請求をされて、よくよく調べてみたら、親が勝手に子供である自分を借金の保証人にしていたというケースがあります。
この場合は、自分の知らない間に勝手に借金の保証人にされていて、本人の同意がないため、返済義務は一切ありません。
親がしたことだからといっても、子供が保証人の同意をしていない以上、子供にはその借金の返済を拒否する権利があるのです。
もし承諾なしに借金の保証人にされてしまったのなら、債権者に対して保証人から外すように請求することができます。
しかし、債権者が保証人を外すという請求に応じてくれない場合もあり、この場合は訴訟を提起する必要もでてきます。
保証人から外して貰うために訴訟が必要となった場合は、その相談を弁護士にするとよいでしょう。
親の借金を子供が肩代わりする場合

子供が親の借金の保証人になっていた、あるいは親が死亡して親の借金を相続したのでなければ、子供が親の借金を肩代わりする法的な理由はありません。
ですが、親が借金返済で困っていたら、親を助けてあげたいという方もいると思います。
子供に法的な返済義務がない場合でも、子供が自分の意志で親の借金の肩代わりをすることは、何ら問題はありません。
ただし、子供が親の借金を肩代わりする場合は、親の借金の原因をきちんと把握しておく必要があります。
親の借金原因が分かっていないと、せっかく借金を肩代わりしたのに、また親が借金を作ってしまう可能性があります。
親の借金の原因が肩代わりをしても良いと思える場合、あるいは親の借金の再発防止ができる場合だけ、肩代わりをするのが良いと思います。
親の借金を肩代わりしたなら
親の借金の肩代わりをしたなら、親に見返りを求めるか求めないかは肩代わりした本人の自由ですが、見返りを求めたい場合には、次のことができます。
親の住宅ローンを肩代わりしたのなら、抵当権が設定されていた親の家を、親の名義から自分の名義に変更して貰う。
親が亡くなって、遺産相続の話しになり、相続人が複数名要る場合には、遺産分割の際に親の借金を肩代わりしたことを主張して、その分、多く遺産をもらう様にする。
経済的に余裕があるのなら、借金の肩代わりの見返りを求めない方が潔くて良いと思いますが、経済的に余裕がない状況なら、肩代わりした見返りを求めても良いと思います。
親に多額の借金があることが発覚したら?
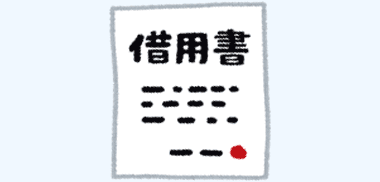
親は確実に子より先に亡くなる確率が高いです。
親に多額の借金があると、親が亡くなるという不幸が襲ってきたときに、借金と共に泣く泣く家も一緒に相続放棄してしまう羽目になりかねません。
そんなことがないように、親が元気なうちに親の借金について把握しておく必要があります。
親の借金の把握方法
親から直接聞く
親の借金状況を調べるための最も良い方法は、親から直接教えてもらうことです。
ただし、親が多額の借金を抱えていた場合、「子供には迷惑を掛けたくない」、「子供には弱みを見せたくない」といった思いから、親自身から言い出すことはあまりありません。
ですから、親に借金があるようなら自分の方から親の借金状況について聞くようにしましょう。
きっぱりと「借金はない」と言ってくれるのなら良いですが、曖昧なことを言ったり、はぐらかす様だったら、まず間違いなく借金があるので、正確な借金の状況について問いただしましょう。
自分で調査をする
親が多額の借金をしている場合は、親の持ち家や土地などに抵当権が設定されている可能性が高いです。
抵当権とは、借金の返済ができなくなった場合に、抵当権を設定した物に対して、抵当権を持つ債権者は他の債権者に先立って借金の弁済を受けることができる権利の事です。
親が所有する不動産に抵当権が設定されているかは、登記情報を調べればわかります。
登記情報は、法務局にわざわざ出向かなくても、インターネットを使えば簡単に調べることができます。
親の所有する不動産に抵当権が設定されていた場合は、親には確実に借金があります。
自分で調査をする(親が死亡した際)
また、不幸にも親が亡くなってしまった場合には、相続が発生します。
生前に親が借金を含めた資産内容を相続人にきちんと説明をしていれば問題ありません。
でも、生前に資産内容の説明を受けていなかった場合は、自分で調査する必要があります。
まずは、親が契約した借入契約書や借用書などがないかを調べましょう。
金融機関から借り入れをしていそうな場合には、借入先が分かればその金融機関に直接、借金について問い合わせをしましょう。
もし、借入先が分からない場合は、個人信用情報機関に情報開示を行います。
個人信用情報機関とは、個人の借入状況のデータを保管している機関です。
個人信用情報機関の情報開示は、本来なら自分自身の情報しか開示請求できませんが、相続人であれば親の情報の開示請求をすることができます。
個人信用情報機関には、次の3つの機関があります。
個人信用情報機関を利用する
- 全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センター
- CIC
- JICC
全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターでは、銀行の借金状況を調べることができます。
全国銀行個人信用情報センターの情報開示手続きは、郵送でのみ可能です。
CICとJICCでは、クレジットカードや消費者金融の借金状況を調査できます。
CICとJICCの情報開示請求は、インターネットと郵送、所定の開示窓口で行うことができます。
団体信用生命保険の加入有無を調べる
また、亡くなった親が住宅ローンの返済をしていた場合には、団体信用生命保険に加入しているのかも調べましょう。
もし親が団体信用生命保険に加入をしていたなら、住宅ローンの残債は保険会社が弁済を行ってくれます。
親が保証人になっていた場合
もっとも調査が難しいのが、親が誰かの保証人(連帯保証人)となっていた場合です。
親が亡くなった場合は、親の保証人の地位は相続人に受け継がれます。
親が誰かの保証人になっているかの調査はとても難しいです。
もし、生前に親から保証人(連帯保証人)の話しを聞いていた場合は、状況に合わせて必要があれば相続手続きの際に「相続放棄」或いは「限定承認」を選択する様にしましょう。
「相続放棄」・「限定承認」とは相続方法の一種で、後ほど詳しく説明をします。
親の借金の解決方法
親の借金の解決方法には、借金の時効を狙うなどの実現性の低い方法もありますが、ここでは確実に実現できる親の借金の解決方法について紹介をしています。
親の家計の支出を改善
親の借金返済が楽になるように、親の家計の支出をチェックしてあげましょう。
親から家計簿を見せて貰い、光熱費や食費などの各項目を確認して、節約できる項目を洗い出しましょう。
節約を実現出来たら、その分を借金返済に充てることができ、親は借金を早期に完済できる様になります。
親に債務整理を勧める
もし、親の借金が節約をしても返済が困難な状況の場合は、親に債務整理をすることを勧めましょう。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を利用することで、借金の減免を実現する借金の整理の事です。
債務整理の手続きは、法律知識が必要な場合が多いので、通常は債務整理をついて熟知した弁護士または司法書士に仕事を依頼します。
債務整理の方法には、主に5つの方法があるので、順に説明をしていきます。
自己破産
返済が困難な状態で、借家住まいの方にお勧めしたい方法です。
裁判所に依頼者の代理人である弁護士が、破産の申立てを行います。
高額財産は全て失いますが、滞納した税金などの非免責債権を除いて、すべての債務が消滅します。
借金がゼロになるので、自己破産後は借金返済をせずに済みます。
過払金返還請求
債権者である貸金業者に借金返済をする際に、利息分を余計に支払っていた場合に、その利息分の返還を求める手続きです。
債務者が債権者に余計に支払っていたお金のことを「過払金」といいます。
長期に渡り借金返済を続けている場合には、過払金が発生している可能性があります。
過払金の有無の調査は、債務整理を手掛けているほとんどの法律事務所または司法書士事務所で無料で行っています。
過払金がある場合は、現在の借金元本と相殺を行い、借金元本の減額を行います。
任意整理
裁判所を介さずに、債権者と返済負担を軽くする為の和解交渉を直接行う債務整理方法です。
借入元本の減額は過払金がある場合は、過払金分を借入元本から差し引くことで実現します。
また、将来の利息なしや遅延損害金が発生している場合は、その支払いの免除などを債権者に求めます。
裁判所を使わないので費用負担が少なくて済み、債務整理に掛かる時間も最短3カ月と短期で済みます。
個人再生
自宅を持っているが手放したくないという方に、お勧めの債務整理方法です。
住宅ローン特別条項の適用を受けることで、マイホームを手放さなくても、大幅に借金を縮小できます。
個人再生を利用するには「住宅ローン以外の借入残高が5000万円以下」、「将来的に安定した収入を得られること」という2つの条件があります。
自分で立てた再生計画に従って、3年間の分割払いで完済します。
特定調停
簡易裁判所で調停委員が仲裁役となって、債権者と債務者の利害調整を図ります。
「過払金と借金元本との相殺」や「今後の利息なし」などの実現を目指します。
話し合いがまとまった場合には、調書を作成します。
もし、親に返済するのが難しい程の多額の借金があったら、ぜひ債務整理を勧めて下さい。
何が一番メリットが大きい借金整理方法なのかを親と一緒に考えて、できれば債務整理の手続きも手伝ってあげるようにしましょう。
親が亡くなった場合に借金の肩代わりを避ける方法
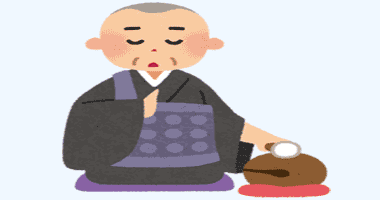
親の借金は親のものだから子供には一切関係ないのですが、親が亡くなった場合は状況が変わってきます。
親が亡くなると遺産相続をしなくてはならず、持っていた財産は子や配偶者など家族に分配されます。
その相続財産は貯金、不動産といったプラスのものだけではなく、借金を含むマイナスの財産も含まれています。
遺産相続者と遺産の分割について
亡くなった親に遺言書がなく、遺産分割について親が何も要望をもっていなかった場合には、親が亡くなった時の遺産相続者は法定相続人となり次の様になります。
親の配偶者は既に亡くなっている状態で親が亡くなった場合
子供が一人っ子だった場合は、その子供が法定相続人となり、全額を相続します。
子供が複数名いた場合は、子供全員が法定相続人となり、親の資産(負債)は子供で均等に配分します。
親が亡くなり、片親の配偶者は存命な場合
存命の親と子供が法定相続人となり、存命の親が1/2、子供が残った1/2の資産(負債)を均等に配分します。
相続人間での合意による遺産分割を行った場合
上記で、遺産の分割割合を示しましたが、相続人間の合意により、上記の分割割合とは異なる任意の分割割合で相続を行うことができます。
この相続人間の合意に基づく遺産分割ですが、あくまで相続人間の取り決めで、債権者にとっては関係ない話となります。
つまり、相続人間の合意に基づく遺産分割に債権者が合意をしていなければ、債権者は各相続人の法定相続分に従って、各相続人に借金の返済を請求することになります。
具体例を挙げると、兄と弟の二人兄弟で、両親が亡くなって相続を受けたとします。
兄と弟の合意による遺産分割で、兄は遺産の3/4、弟は遺産の1/4を相続で引き継いだとします。
この場合でも、債権者は相続によって引き継がれた借金の返済を兄に1/2の金額、そして弟に1/2の金額、請求することができます。
相続で借金を負いたくない場合の対処法
借金を負っている親が亡くなった場合、そのままだと相続により、相続人が借金を負うことになります。
相続により、想定外の借金を相続人が負うのを救済する目的で、「相続放棄」と「限定承認」という制度が用意されています。
これらの制度を利用することで、親の借金を引き継ぐのを避けることができます。
相続放棄
相続放棄とは、マイナスの借金だけでなくプラスの財産も相続する権利を一切失う手続きです。
借金返済の義務を負いたくない場合は、相続放棄をすれば大丈夫です。
また、相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなくてはいけません。
プラス財産が多く借金がそれほど多額じゃなければトータルして相続した方がお得になることもありますが、借金の額が大きい場合は相続放棄を考えておきましょう。
なお、相続放棄は親の財産を放棄する手続きなので、次の様に少しでも親の財産を相続する行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる場合があります。
相続放棄が認められなくなるケース
- 親が亡くなった後に、親の銀行口座からお金を引き出して使った。
- 親が亡くなった後に、親名義の不動産を自分名義に変えた。
- 親が亡くなった後に、親が借入した借金の返済をした。
上記の様な行為を行うと、相続放棄が認められなくなり、親に多額の借金があった場合でも相続しなければならなくなるので、注意する必要があります。
なお、相続放棄した場合でも、親の生命保険は受け取れる場合がほとんどです。
相続放棄をしても、親に掛かっていた生命保険の受け取りが可能かは、保険の契約内容を確認するか、または保険会社に直接確認をすると良いです。
限定承認
限定承認とは、相続するブラスの財産の範囲内でのみマイナスの借金も相続するという手続きです。
例えば、相続の際に、プラスの財産が300万円、マイナスの借金が100万円あったとします。
この場合は、マイナスの借金よりプラスの財産の方が多いので、マイナスの借金100万円は全額、相続します。
一方、相続の際に、プラスの財産が300万円、マイナスの借金が500万円あったとします。
この場合は、マイナスの借金はプラスの財産と同額の300万円だけを相続をします。
つまり、限定承認を行うことで、プラスの財産よりマイナスの借金の方が多くなる赤字になる相続を避けることができます。
離婚して別居中の親に多額の借金があり、亡くなった場合
離婚をすると元妻や元夫には、配偶者としての相続人の権利は無くなります。
ですが、子供がいた場合には、例え親が離婚をしたとしても、子供には相続人の権利があります。
そのため、例えば父親に多額の借金があり、借金を理由として母親が離婚をして子供と一緒に別居をしていたとします。
父親が亡くなった場合には、母親は相続人とはなりませんが子供は相続人になります。
子供が父親と絶縁状態となっていて、父親が亡くなった場合には、突然、父親が作った借金の返済請求が子供に来ることがあります。
この場合は、早急に父親の遺産内容を調査して、必要があれば早急に「相続放棄」や「限定承認」の手続きを採る必要があります。
親が失踪をした場合に借金の肩代わりを避ける方法

多額の借金を抱えていた親が失踪をして行方不明となった場合は、その借金返済を子供が負う義務は生じるのでしょうか?
法的な失踪手続きには「普通失踪」と「特別失踪」があります。
普通失踪とは、失踪者の生死が7年間不明な時に家庭裁判所に申立てることで失踪宣告ができます。
特別失踪とは、震災や船舶の沈没等によって生死が不明となって、危難が去ってから1年間生死不明の場合に、家庭裁判所に申立てることで失踪宣告ができます。
失踪宣告をすると、法的に失踪者は死亡したものとみなされて、相続が開始することになります。
このため、失踪した親に多額の借金があった場合には、失踪宣告をしないことで、相続を回避することができます。
普通失踪と借金の時効の関係
借金の返済請求には時効があり、金融機関からの借入の場合は5年、個人からの借入の場合は10年が時効期間となっています。
普通失踪の場合は、失踪宣告ができるのは失踪をしてから7年後なので、金融機関の借金の時効期間5年を経過してからとなります。
このため、親の借金が金融機関からの借入で、かつ普通失踪であれば、親の借金を受け継がずに相続できる場合があります。
普通失踪の失踪宣言をして親の遺産を相続した後に、すぐに借入先の金融機関に対して借金の時効成立手続きである「時効の援用」を行います。
「時効の援用」手続きを行うことで、親の借金を負うことなく相続を受けることができます。
但し、借金の時効を狙う場合には、注意すべき点があります。
借金の時効期間の経過途中で、失踪中の親に対してお金を貸した金融機関が貸金返還請求訴訟を提起した場合、借金の時効期間はゼロから再スタートとなります。
すると、普通失踪の失踪宣告ができる7年が経ったとしても、借金の時効期間に達していない場合があります。
ですから、借金の時効を狙う場合は、借入先の金融機関によって貸金返還請求訴訟などの時効期間をリセットする手続きが行われていないかを調査する必要があります。

